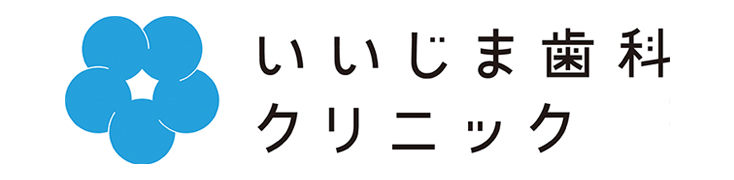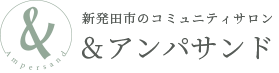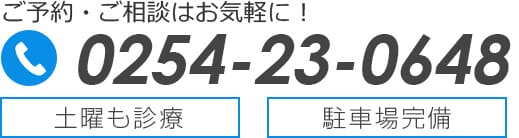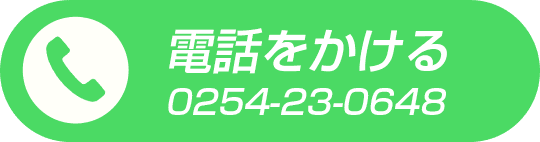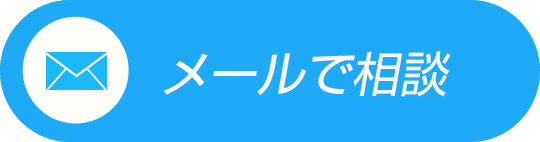新歯界の投稿より
先日、歯科医師数の抑制の動向について触れましたが、
以前、新潟県歯科医師会の月刊誌にこの件に関して投稿したことがありました。
今日は、その内容を紹介いたします。
我々業界人向けに書いたものですので、一般の方が読むとどちらかというと歯科医師の利害に関して目が行くかもしれませんが、そういう意図ではなく、我々歯科医療にかかわる人員が意図的に削減されていることにより、国民皆さんの健康の保持が難しくなっていくことへの警鐘と取っていただければ嬉しいです。
この機会に以前から思っているいわゆる歯科医師需給問題に関して私見を述べたいと思います。
平成26年のデータで歯科医師数は103.972人、人口10万対歯科医師数は81.8人とされています。
歯科医院の経営状態悪化やワーキングプアなどの報道等を見なくても、我々歯科医院経営者は、現状の歯科医師数が過剰な状態であることは,痛い程日々感じています。
歯科医師不足が深刻化していた「むし歯の洪水の時代」昭和44年に10万人対歯科医師数50名という目標を閣議決定し、次々に歯科大学の新設が認可され当初の入学定員約1,100名から、一気に3,000名台となり、近年の状況に至っています。そのため、昭和61年厚生省「将来の歯科医師需給に関する検討委員会」の最終意見に基づき、昭和62年削減計画(大学歯学部・歯科大学入学定員の20%削減目標)が示され、更に厚生省は平成10年5月には更なる10%削減を求めました。また一方で、医道審議会歯科医師分科会下の「歯科医師国家試験制度改善検討部会」において現行の歯科医師国家試験の合格基準の引き上げが歯科医師数の抑制を目的として平成18年に確認されました。国、歯科医師会、歯学部大学の合意の下、入学者数と国家試験合格者数を減少させることにより歯科医師数の抑制がここ、10年間以上行われてきたわけです。その結果、近年の国試験合格者数は年間2,000名を切っています。なお、日本歯科医師会は平成26年の「歯科医師需給問題の経緯と今後の見解」において年間の新規参入歯科医師数は1,500名程度が上限と、さらに高い抑制を求めています。
私は、この傾向に2点疑問を呈しています。
①このままの歯科医師数抑制は行き過ぎではないか
②問題の本質は歯科医師数ではなく別にあるのではないか
10年後、20年後の未来の話です。
1点目、歯科医院診療所に在籍する現在の歯科医師の最大階層は50~60才であり、平均年齢は52才(平成26年12月31日現在)。これらの層が今後10から20年で一気に引退、多くは廃業します。
また、20歳代の歯科医師の半数は女性になってきており、男性に比べて開業する割合がはるかに低く、卒後10年でその実動率は3~4割程度とも言われています。また、勤務医になる歯科医師もいるであろうから国試合格者2,000人のうち、実際に診療所を開設する人数は1,000人程度になってしまうのではないでしょうか。これでは昭和40年代に逆戻り。それで現在の高度な地域医療を維持することが本当にできるのでしょうか。しかもその傾向は都市部より新潟のような地方部に間違いなく先に表れてくると危惧しています。そろそろ、歯科医師数の抑制という数の呪縛から将来への展望へと舵を取り換えなければ、大切な国民の口腔健康を守ることができなくなってしまうのでは無いかと危惧しています。
むし歯の洪水対策が大きな目標であった時代に立てられた人口10万対歯科医師数50人という数値。その数字の根拠は良く分りませんが,人口の減少と虫歯の激減からだけ鑑みてみると確かに歯科医師数は少なくなってよいとの理屈になるのかもしれません。
私は問題点はそこにあるのだと思います。
大量のむし歯と戦い、その結果生み出された補綴処置が仕事の大半であった以前とは、我々歯科医師が向き合うべき歯科医療の問題・課題点は,大きく変ってきています。
むし歯を修復した後や歯周疾患の維持管理を目的とした予防的メンテナンスの重要性の増大。顎関節症やブラキシズムなどの異常習癖への対応、さらに口腔領域に関連した摂食や嚥下の問題。口呼吸に代表される呼吸の問題とその疾患への対応。食習慣や食生活歯指導だって歯科医師の仕事だと思います。その他、その悪影響を考えると不正咬合だって立派な疾患であると思います。私たちにはまだまだ多くのニーズがあり、しなければならないことがたくさん残っています。ですが、これらはほとんど、医療保険からの給付が無いかあるいはとても低い評価にとどまっています。つまり、収益が見込めないか自費診療という高いハードルを越えなければならないのです。往診や在宅診療だって多くの歯科医師が大切なこととわかってはいても、診療所から出かけていくというストレスと労力に見合わない対価にまだまだ二の足を踏んでいるのだと思います。地域保健活動だって立派な歯科医師の仕事です。
我々がしなければいけない仕事は沢山あります。その仕事量から考えて見たとき、歯科医師の数が多すぎるとは私は思っていません。すなわち二番目の問題点は「歯科医師の数が多いのではなく、歯科医師が食っていけないことにある。」
ただ、実際に食べていける(対価を得られる)仕事の種類がここ何十年も変化なく、虫歯の減少によってそのパイはどんどんどんどん小さくなっていくばかりです。ですので、もっと私たちが食べていくことができる仕事を増やしていくことが肝要だと思います。では、どうすればいいのか?歯科医師数の抑制ではなく、その点を真剣に考えて実行する時期に来ているものと考えます。
インプラント講演会
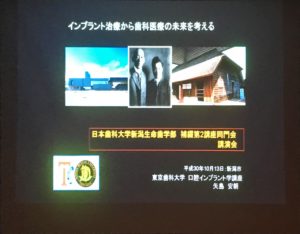

10月13日
日本歯科大学新潟生命歯学部歯科補綴学第二講座同門会・学術講演会でした。
年に一回開催される大学医局員と補綴講座に在籍したOB向けの専門性の高い講演会です。
ここ数年、私は司会座長を務めさせていただいています。
今年は口腔インプラント学会常務理事で東京歯科大学口腔インプラント学講座教授そして水道橋病院病院長の矢島安朝先生をお迎えしました。
矢島先生はもともとは口腔外科学を専門にされています。口腔外科とは口領域の手術などを専門とするスペシャリストです。我々歯科医師にはいろいろな仕事がありますが、多くの歯科医師は私もそうですが、歯や歯茎の病気、すなわち虫歯と歯周病の治療そして歯がなくなった人に義歯やクラウンなどを入れることを主にする「いわゆる一般歯科」です。口腔外科医は一般歯科の仕事はあまりせず、おもに腫瘍の手術や骨折などの外傷処置を専門的にします。当然、全身的な管理法も収得しています。
ですので、我々一般歯科医では手に負えない、例えばリスクの高い患者さんは口腔外科医に紹介することとなります。
インプラントという技術はじつは、歯として機能させるといういわゆる歯の形態的な再現技術と、インプラントという材料を生体内に埋入するという口腔外科的な技術が融合されたテクノロジーです。
現在はインプラントそのものが学問として確立してきていて、インプラント学となっていますが、黎明期には私のようないわゆる一般歯科医(特に補綴医)からのアプローチと口腔外科医的なアプローチと二つの流れがあったものです。
矢島先生は口腔外科のスペシャリストとしてインプラントに関わったため、私たちの視線とはまた切り口の違った講演で大変有意義でした。
特に顎顔面領域の解剖の説明は、基本的な知識の重要性を再認識させてくれるものでした。
一般医が必要な観血処置の緊急時の対応法も簡潔に詳しく教えていただき、どれもがすぐに臨床に役立つことばかりでした。
そして
講演の後半は我が国の歯科医療の将来について話されていました。
歯科医師過剰時代といわれ続けて久しく、日本ではずいぶん前から歯学部の定員削減と歯科医師国家試験の合格人数抑制が続いています。歯科医院の数にはまださほど影響があるようには見えませんが、じきに団塊世代の歯科医師たちが引退し始めますから、街から歯科医院がどんどん少なくなってしまう現象がほどなくやってくると思います。
口腔は健康の源であります。それを担うべき歯科医師がどんどん減っていくことはだれにとっても良いこととは考えられません。国民にそのことを伝えていくべきとの矢島先生のお話、もっともだと共感しました。
私たち歯科医療に携わる立場の人間がもっと発信していくべきことだと思います。
このテーマについては、また後日掲載したいと思います。
インプラント治療の流れ
今回はインプラント治療の流れをご説明します
①インプラントをする前に・・・
お口の中の環境を改善しましょう!!
むし歯・歯周病などの治療を終了させる
全身的な問題はないでしょうか?
糖尿病や高血圧など体の管理もしっかりと
たばこもやめましょう
禁煙をサポートする禁煙外来なども活用しましょう
②インプラントのための検査
レントゲン、口の中の精密検査、模型による検査を行ます
CTなどで3次元的に正確な検査を行うことが必要です
③インプラント埋入手術
検査結果に基づいてインプラントを設置する手術を行います
必要に応じて骨を増やす手術を事前に行ったり併用することもあります。
④インプラント2次手術
設置したインプラント体を歯が作れるように準備する手術です
いいじま歯科クリニックでは安心安全と確実な手術を行うためこの方法を採用しています。使用しているインプラントシステムや口の中の環境によっては行わない場合もあります。
⑤歯を作る処置を行います
型取りをして歯を製作します
歯が入って終わりではありません!!
⑥メインテナンス
歯が入った後、定期的にチェックを受けましょう。
あくまでも口の中に外から入れたものです。定期的なお手入れが長持ちにつながります。
簡単に紹介しましたが、使用しているシステムや口の中の環境によって治療期間や方法が異なる場合があります。お近くの歯科医院でお尋ねください。インプラント治療は保険外治療(自費治療)です。医院によって料金が異なります。またインプラントをやっていない医院もあります。
MRC院内勉強会
8月30日に院内勉強会を開催しました。 院内勉強会は月に一回スタッフ各自がテーマ―ごとに自分で調べて勉強したことを発表する場です。 そのうち、年に一回は医院外から講師をお招きして研修や講演をしています。
今回は静岡市のアヒルの子歯科・ こども矯正⻭科クリニック院長の塩⽥ 雅朗をお招きして開催しました。
塩田先生は Dr. Chris Farrellが考案した筋機能訓練を取り⼊れた⻭列矯正治療法Myofunctional Research Co.(MRC)の我が国での第一人者でパイオニアです。
年間何度か全国の歯科医師やスタッフ向けの講演会を開催されていて、その講演会は100人を超える定員がいつも満席になってしまうほど今、注目を集めている先生です。
MRCは顔面の発達の改善、非抜歯治療、そして、真の歯の配列の安定性という強固なコンセプトを持っています。
歯並びは呼吸や嚥下習癖、姿勢などによって顔貌の発育が不正になったときに乱れてくるものとの原因論が根底にあります。そのため、子供の習癖・呼吸嚥下の機能を正しく治すことによって顔貌 の良好な発育を得ることができ、その結果として歯並びがきれいになりますし、今までの矯正治療のように矯正治療後の後戻りを防ぐための保定の必要性もなくなります。
そして⼦ども達に正しい姿勢と⿐呼吸を習慣づけることは、その子の生涯の健康への貢献につながります。
私は、塩田先生の講演を始めてお聞きした時に大変な衝撃を感じました。とともに、MRC治療に大きな可能性を見出しました。
私を含め一部のスタッフは何度か塩田先生のクリニックを訪問して、色々教えていただいて面識はありましたが、大変お忙しい先生ですので、いいじま歯科での講演をお願いするにあたって受けていただけるかは、半信半疑でした。
今回、ご快諾いただけて正直驚きました。とともに、先生のMRCにかける大きな思いを感じもしました。この講演会でスタッフに直接ご指導いただけたことは大変な喜びであります。
今後、MRC治療につきましてさらに深めていきたいと思っています。
また、一緒に受講いただいた新潟市うめつ歯科医院のスタッフさんと梅津先生。遠く盛岡からご参加いただきましたゆいとぴあ歯科の藤本先生、あ本当にりがとうございました。

予防歯科講習会
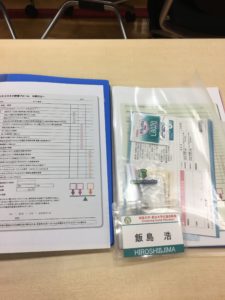
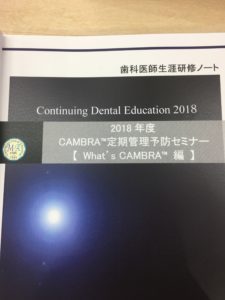
今年は毎日とても暑い日が続いています
東北生まれの私はもともと暑さに弱かったので、新潟に来た時にこちらの夏の暑さに大変驚きました。
それでも35度を超える日なんてなかなかなかったですけれど、今は平気で超えちゃいます。
本当に気候はどうなっちゃってるんでしょうね。
今週末は、衛生士スタッフ二人と猛暑の新宿で予防歯科の講習会を受けて来ました。それにしても東京は異常に暑いです
歯科界で予防の先進地域といえば、スウェーデンやフィンランドに代表される北欧といえます。予防歯科の研究と実績そしてその歴史は確固たるものがあります。事実、日本における予防歯科の実践は北欧に学んでいることが多々あります。
今回学びに行ったのは実は北欧型ではなく、アメリカはカリフォルニア州発祥のいわゆる北米型の予防歯科システムCAMBRAです。
CAMBRAとはCaries Management By Risk Assessment ~リスク評価に基づくう蝕管理~の略称でカリフォルニア大学サンフランシスコ歯学部長のフェザーストーン教授が提唱するう蝕予防法です。
その考えは
う蝕は「う蝕を誘発する疾患指標とリスク因子からなる病変因子」と「う蝕を遠ざける防御因子」の2つのバランスによって発生するという原則から、エビデンス(過去のデーター)に基づき、過去のう蝕経験や唾液量などから個々人のう蝕リスクを評価し、それに応じたリスクを下げるための処置がメニュー化されて提供されるところが最大の特徴です。
今まで、歯科医師や歯科衛生士の経験値や知識によってさじ加減でなされていた予防プログラムが、患者さん一人一人向けにきめ細やかに提供されるという、しかもそれが、データーに基づいて科学的に実証されているということが何といっても長所であります。
う蝕は子供の疾患。と一世代前では言われていましたが、現在は歯科医療も進んだために高齢者の方の歯を残すことができるようになりました。また、寿命が延びたために高齢の方の歯の重要性も上がってきています。そのため、この世代の方へのう蝕予防が必須となってきています。
予防歯科
これからの歯科医療のキーワードになっていくのだと思います。
この春から続いていた怒涛の出張と研修の旅も今回でちょっとひと段落です。
お盆お休みにも入りますから、少しクールダウンして外で学んだことをいったん整理して、医院に入れていきたいと思います。またいろいろな方との新しい出会いも刺激的でしたし、これからの様々な発展を予感させてくれます。
何といっても、日ごろとても忙しい業務の日々なのに、一緒に学びの旅に出向いてくれるいいじま歯科のスタッフさんたちに心から感謝しています。
いつも未来を見つめて
予防歯科医院を見学に

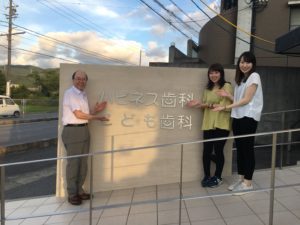
今回は愛知県にあるハピネス歯科こども歯科さんにスタッフの石山、松坂両衛生士と見学に行ってきました。
ハピネス歯科さんは開院してまだ2年の若々しい医院さんです。
そして、なんといってもその特徴は医院方針のど真ん中に「予防歯科」を据えていることです。
院長の稲吉先生とは彼がまだ勤務医だった時代にセミナーを通じ知り合いましたが、それからお互いに様々な情報を交換し合うような仲になりました。出会ったときは彼はまだ20代後半。ですがその知識量と実践力に圧倒されました。
そして、そんな彼から筋機能矯正MRCだったり、予防歯科システムの情報だったりを知ることができ、それらがいいじま歯科の方向性に大きな影響を与えてくれています。
ハピネス歯科さんの地を訪れるのはもう、3回目です。
開業3年目にして、すでに一日に100人を超える患者さんが訪れる超人気歯科医院になっています。
患者さんに支持されているのは何といってもハピネス歯科さんが稲吉院長の信念である「予防」を医療のセンターにどっしり据えているからだと確信を持って言えます。
いいじま歯科の歯科衛生士二人と一緒に医院を訪問して、たくさんのことを学んできました。これらの貴重な体験を医院に還元できる日も近いと思います。それがまた楽しみです
お忙しい中で、私たちに丁寧に対応くださった稲吉先生とハピネス歯科のスタッフさんに心からお礼申し上げます。
いつも未来を見つめて