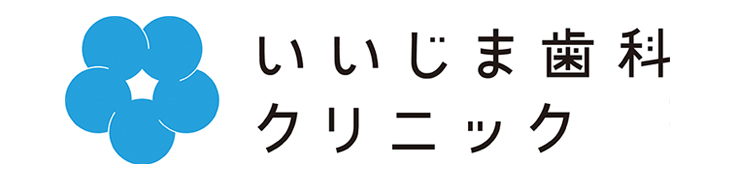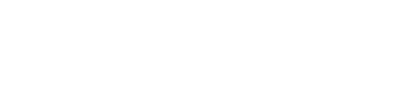第68回秋季日本歯周病学会 in 新潟(朱鷺メッセ)に参加してきました。
皆さんこんにちは。
いいじま歯科クリニック勤務医の大藤です。
先日、朱鷺メッセ新潟コンベンションセンターで開催された「第68回 秋季日本歯周病学会」に参加してきました。今回は10月18日(土)に参加し、シンポジウムやセミナーを通して多くの学びがありました。

久々の再会と学びの時間
開催地が地元・新潟ということもあり、参加しやすい学会でした。前日には私の母校である昭和大学歯周病学講座の先生方とも久しぶりに再会でき、懇親会では近況を語り合い、和やかな時間を過ごせました。
学会シンポジウムは「抗菌薬の適正使用」「高齢者の歯周治療」「MRONJ」の三本柱で構成、どの講演も日常臨床に直結する内容でした。
歯周病の病因と細菌の概念
近年、歯周病の病因は特定の悪玉菌(レッドコンプレックス)だけではなく、「口腔内細菌のバランスの乱れ(ディスバイオシス)」によるものと捉えられるようになってきています。
特にP. gingivalisなどの菌はキーストーン病原体として重要視されています。キーストーン病原体は、歯周病の発症や進行において、他の微生物との相互作用や宿主の免疫応答に影響を与え、病気の進行を助長する重要な要素とされています。キーストーン病原体を中心とした微生物間でも何らかのネットワーク(コミュニケート)を構築しており、他微生物との相互作用により歯周病の進行悪化に関与するという考えが注目されています。とても興味深い内容でした。
抗菌薬の適正使用
抗菌薬は必要な場面で適切に使うことが重要で、「耐性菌」の増加を防ぐ必要があります。バイオアベイラビリティ(生物学的利用能)が高い(服用した薬が効率よく血流に移行する)薬剤の選択が重要です。
これまでのガイドラインで汎用されてきた一部の第3世代セファロスポリン系薬剤などは、バイオアベイラビリティが低く(組織移行性が悪い)、耐性菌を生みやすいことから、使用を控えるべきであるとのことでした。日々臨床でも抗生剤の処方を行っていますが、フロモックスなどのバイオアベイラビリティの低い抗生剤を処方していたため、今一度投薬の見直しをする必要性があると感じました。
従来使われてきた一部の抗菌薬は、効果が不十分で耐性菌を生みやすいため、見直しが進められています。現在のガイドラインでは、第一選択薬はアモキシシリンで、ペニシリンアレルギーの患者さんには
クリンダマイシン(ダラシン®)等の処方を推奨しています。
また、歯周病の急性症状(P急発)には、ミノサイクリン軟膏などの局所投与が有効で、SRP(スケーリング・ルートプレーニング)への全身抗菌薬の補助的併用は、エビデンスが弱く、弱い推奨にとどまっています。
高齢者の歯周治療と課題
日本の高齢化が進む中、80歳以上でも歯が多く残っている方が増えています。その一方で、重度の歯周ポケットを持つ方も増加傾向にあります。
高齢になると通院が難しくなるため、在宅や施設でのケア体制づくりが重要です。歯科医師、看護師、介護職など多職種による連携が求められています。
オーラルフレイルへの対応
「オーラルフレイル」(口腔機能の低下)は早期発見が大切です。チェック項目に複数該当する方は、精密な検査が必要です。
外来が可能な高齢者には、清掃しやすいシンプルな口腔環境づくりが基本であり、外科処置は控えめに。要介護者には主に衛生管理を中心としたケアが行われます。
骨の薬とあごの病気(MRONJ)
骨粗しょう症の治療薬(ビスフォスフォネートやデノスマブ)は、あごの骨の壊死(MRONJ)を引き起こすことがあります。
最新の見解と治療方針
2023年の最新指針では、「感染源となる歯は早めに抜歯や治療を行う方がよい」とされており、従来の「抜歯を避ける」方針から大きく変わりました。
また、「薬を一時中止(ドラッグ・ホリデー)することで予防できる」という説にも、十分な根拠はないとされ、現在では休薬しないことが提案されています。
治療の目標も、「生活の質(QOL)維持」から「治癒(Cure)」へとシフトしており、全身状態が許せば外科的治療が優先される傾向にあります。
学会シンポジウムでの講演内容も非常に学びが多かったですが、臨床ポスターにおける他の先生方の症例を拝見することが出来てとても勉強になりました。すごい症例を目の当たりにし、改めて歯周病治療の奥深さを痛感しました。
おわりに
今回の学会では、日々の診療に活かせる多くの学びがありました。最新の知見を得たり、刺激を周りから貰えるという点で、学会参加は非常に有意義であると改めて感じました。今後も、旧知識をずっと保持するのではなく、アップデート・広げるという視点で学ぶ姿勢を持っていきたいと思います。
最後まで読んで頂きありがとうございました。